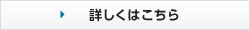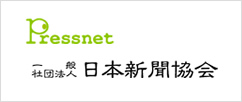この団体について
この団体について

全国の新聞、放送、出版、広告など201の団体・法人で構成されています。
組織概要、沿革のご紹介です。
 活動紹介
活動紹介
 TOPIX
TOPIX
「戦後80年の分岐点―メディアは民主主義を支えきれるか」をメインテーマに
第67回全国大会を福井市で開催
マスコミ倫理懇談会全国協議会10月9、10の両日、第67回全国大会を福井市の「フェニックス・プラザ」で「戦後80年の分岐点―メディアは民主主義を支えきれるか」をメインテーマに開催した。80社・団体からリアルで219、オンラインで58人が参加した。
1日目は徳永康彦・代表理事のあいさつ、吉田真士・福井新聞社代表取締役社長の地元社代表あいさつに続き、「SNS時代の取材・報道とは―戦後80年、揺らぐメディアの信頼」をテーマにディスカッションを行った(写真①)。登壇者は西田亮介氏(日本大学危機管理学部教授)、山口真一氏(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授)、米重克洋氏(JX通信社代表取締役)、司会は斉藤一也氏(テレビ東京報道局総合ニュースセンター エグゼクティブプロデューサー)が務めた。また、「メディアと法」研究会の新規プロジェクト「記者活動に対する誹謗・中傷への制度的・法的対応および支援策の検討」について、澤康臣氏(同研究会客員研究員、早稲田大学教育・総合科学学術院教授)から報告があった(写真②)。


午後は、「真に必要な災害報道とは」「SNS時代の選挙報道の課題」「言論空間におけるスティグマを考える」「記者活動に対する誹謗・中傷への対応」「メディアはAIを使いこなせるのか」をテーマにした5つの分科会を開き意見交換した。
2日目は午前中に全体会議を行い、座長による分科会報告(写真③)と全体討議の後、「私たちは戦後80年という歴史的節目に立ち、メディアの原点を改めて問い直さなければならない。「ジェンダーに基づく暴力」を排し、倫理観を堅持し、責任ある姿勢を貫くことで、民主主義社会の基盤を支える存在であり続ける」との大会申し合わせを採択した(別掲)。

大会終了後、北陸地区マスコミ倫理懇談会の北國新聞社、福井新聞社、北日本新聞社による報告会が開かれた。
来年の第68回大会は11月5(木)、6(金)の両日、広島市で開催予定。
マスコミ倫理懇談会第67回全国大会申し合わせ
戦後、築かれてきた「自由で開かれた国際秩序」は、トランプ米大統領の再登場で大きく揺らいでいる。社会的格差が広がる中で、内向きな「自国第一主義」に経済的繁栄や安全保障の拠りどころを求める動きが広がり、民主主義を支える言論やメディアに対する弾圧が強まっている。ロシアのウクライナ侵攻は3年半たっても出口が見えず、中東の戦禍は「ジェノサイド」と言われるほど深刻化し、混迷は深まるばかりだ。
国内に目を向けても、戦後政治の枠組みが崩れつつある。物価上昇が人々の生活を直撃しているにもかかわらず、有効な政策を打ち出せない与党は、初めて衆参両院の選挙で過半数を割った。多党化の様相を呈する中で、不寛容な言論が広がり、排外主義的な勢力の拡大を許している。気候変動の影響による豪雨災害も多発するなど、社会は不安定さを増している。生成AIの登場により、メディアの在り方が問われている。
昨年来の知事選挙や国政選挙では、SNSが投票行動に大きな影響を与えている。SNSを活用した選挙運動により、これまで政治に距離を置いてきた若い世代の関心を引き寄せる一方、偽・誤情報や扇動的な投稿、誹謗中傷が拡散し、有権者の冷静な判断を妨げる要因ともなった。また、既存メディアが提供するニュースや解説に対して「偏っている」といった批判が高まり、記者や報道機関を敵視するような言動が大きな問題となり、記者を守る対策が早急に求められている。報道することで、不当に人権を侵害する問題も指摘された。
今大会は「戦後80年の分岐点―メディアは民主主義を支えきれるか」をメインテーマとした。社会の分断が進む中、民主主義はかつてない危機に直面している。私たちは戦後80年という歴史的節目に立ち、メディアの原点を改めて問い直さなければならない。「ジェンダーに基づく暴力」を排し、倫理観を堅持し、責任ある姿勢を貫くことで、民主主義社会の基盤を支える存在であり続けることを申し合わせる。
2025年10月10日
- 今後の予定